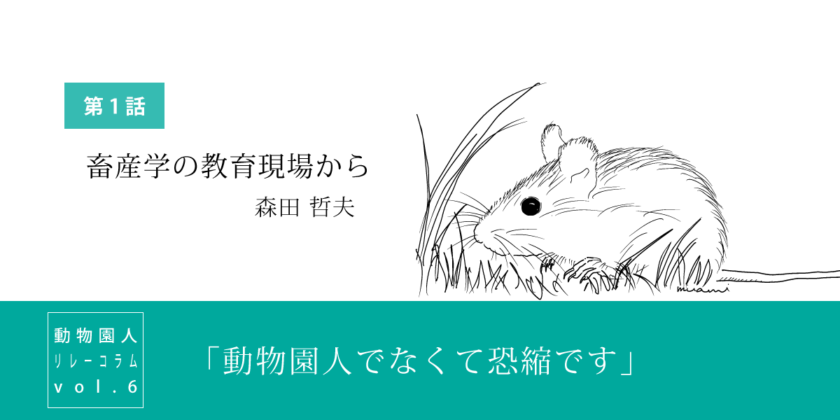
目次
はじめに – 教壇に立った者として
「宮崎大学は教師として私を育ててくれた第二の母校や」とボケをかますと「宮大では未熟者を教壇に立たせていたんかあい」と、ツッコミが匿名で来そうだ。インターネット上に拙い文をさらすことはとても恐ろしい。
何かやらかしそうで不安だが、勇気を出して書いてみた。読んでやってください。
動物園との連携 – 学びの場を広げる
20年足らずの期間ではあったが、宮崎大学農学部の畜産学系教育研究分野(以下、畜産分野と呼ぶ)で教えていた。在任中は、宮崎市フェニックス自然動物園(以下、フェニックス動物園)に、見学、実習、講義、卒論研究と、あらゆる面で協力していただいた。

【出典】宮崎県観光協会
動物園の飼育員になりたい!現実と夢のギャップ
大学で動物園動物と野生動物について学び、将来は動物園の飼育員になりたいと希望する学生が宮崎大学の畜産分野に相当数存在することを、新入生アンケートを通して知った。しかし、動物園飼育員は当時も今と変わらぬ難関。入学時の夢をかなえられる人はほんの一握り。初志貫徹するにも、軌道修正するにも判断材料が必要だろう。
まずは、動物園と動物園飼育員のリアルについて知ってもらうことが大切だと日頃から考えていた私は、学部組織改変の好機に、動物園学を畜産分野の教育カリキュラムの選択科目として新設することを提案した。
全国有数の畜産基地に立地する我が畜産分野は農用家畜の教育研究を通じて地域に貢献することを主たるミッションとしている。この「ガチの家畜がメインストリーム」という暗黙の了解に対し全く異論はなかった。食料の安定供給は人の健康と生命を支える基本だからだ。


一方で、動物生産科学コースを名乗った時代には実験動物一級技術者の在学受験資格認定校に指定され、農用家畜とは異なる、実験動物の教育にも着手している。こんな間口の広さを畜産分野は持ち併せてもいた。
柔軟な気風の下、動物園学の新設は滞りなく進んだ。今から十数年前のことである。国立大学の畜産分野では、岐阜大学とともに動物園学開講の先陣を切ったと思っている。
「実践動物園学」の誕生 – 動物園のリアルを学ぶ
動物園学の講義の分担を宮崎大学畜産学科卒業生の出口智久(としひさ)フェニックス動物園副園長(のちに園長)にお願いした。無償のボランティア講師である。親切なことに、出口さんは「戦う動物園:旭山動物園と到津の森公園の物語」の著者の一人である岩野俊郎到津の森公園園長に声をかけてくださった。謝金なし・旅費のみ支給、宿泊も大学の宿舎利用というブラックなオファーだった。参考文献として「戦う動物園」を受講生に指定してはいたが、毎年40部程度売れたからといって、岩野さんのふところが暖かくなることは決してない。にもかかわらず、岩野さんは遠路はるばる北九州市から来学。
学生たちを前に積もる思いを語ってくれた。4コマを二日でこなす老人には酷な集中講義だったが、若者が好きな岩野さんは軽々とこなした。熱のこもった彼の言葉が学生の心を少なからず動かしたことを授業アンケートで知り、思わず口元が緩んだ。
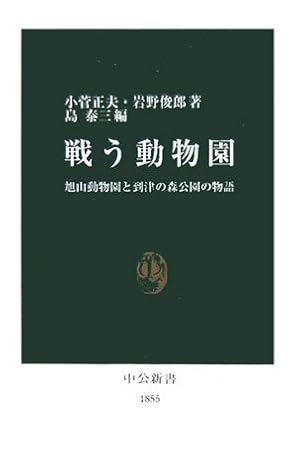
大学法人化の影響を受け研究室の予算が縮小していたので、お二方の力添えは本当にありがたかった。現場経験が豊富な動物園人にしか語ることができない「知恵と技とフィロソフィー」に対する敬意を込め、科目名は実践の二文字を頭にのせ「実践動物園学」とした。
学科カリキュラムの統合整理を経て、実践動物園学は現行の「野生動物・動物園学」に引き継がれている。2025年度からの新カリキュラムでは従来の座学から実験実習に形を変え「家畜・動物園動物管理実習」と「野生動物学実験」としてスタートする。
動物園動物に関連する科目は畜産分野の選択科目としてカリキュラムに定着し、全国で行われている動物園人の後進育成の一端を宮崎大学も担っている。フェニックス動物園と宮崎大学畜産分野の二人三脚は今も順調のようだ。両者の信頼関係のサステイナブルな発展を願ってやまない。
飼育員に必要な素養とは?畜産学との関係
畜産出身の飼育員が動物園で多数活躍していると出口さんから聞いた。小宮輝之元上野動物園園長もそのお一人だそうである。
畜産学は動物の生産を扱うが、動物の生産と飼育は表裏一体の関係にある。動物園動物の飼育は畜産学の応用問題のようなもの。畜産で学んだことは動物園動物飼育の課題解決に必ず役立つ、ということか。
畜産学教育の柱は飼養管理と改良増殖そして製造利用である。このうち飼養管理と改良増殖には農用家畜はもちろんのこと動物全般の飼育の基礎ともなる科目が網羅されている。
畜産学の教育研究分野(研究室)として、飼養管理を栄養学と管理学が、改良増殖を育種学と繁殖学が担うという布陣だ。ただし、製造利用に携わる畜産食品科学は畜産物の加工製造や品質評価を扱い、動物の飼育と直接の接点はない。
動物の栄養管理 – 健康を支える重要な知識
動物栄養学ではウシ・ブタ・ニワトリの栄養について学ぶ。草食性で反芻動物であるウシ、雑食性のブタ、鳥類であるニワトリと、食性と分類が異なる動物の栄養の仕組みを横並びで学ぶことにより動物園動物の栄養の理解に必要な比較動物栄養学の視点が培われる。


一方、飼料学は飼料を自身で設計するのに生かせる。横浜市緑の協会の桐生大介氏は栄養学と飼料学の知識をフル活用して、リクガメなど希少動物の飼料レシピを開発し、さまざまな問題の解決に成功している。このリクガメのレシピ、桐生スペシャルと呼ばれているという。腕のいい飼育員さんとは桐生さんみたいな方を指すのだろう。彼が畜産分野のご出身というのはとても嬉しい。
飼育環境を整える!動物管理の最前線
動物管理学は行動管理、環境管理そしてアニマルウェルフェア(AWとも呼ぶ)を扱い飼育動物の適正飼養とは何かを追究する学問だ。
AWへの配慮が動物園での重要課題となっている現在、農用家畜のAW向上に向けた畜産分野の先進的な取り組みから動物園が学ぶことは多いと思う。農用家畜のAWの詳細については以下のホームページで参照していただける。

血統管理の重要性 – 希少動物の未来を守る
種の保存のため、動物園にいる希少動物を血統登録し管理することも動物園の重要な役割となっている
長年にわたり家畜の遺伝的改良で培ってきた動物育種学の蓄積は動物園動物の血統管理にも適用できる。新潟大学朱鷺・自然再生学研究センターの協力研究員として動物遺伝育種学・統計遺伝学の専門家が名を連ねているのはその証しだといえる。
希少動物の繁殖を支える科学の力
動物園における希少動物の保全では動物繁殖学の活躍が近年目覚ましい。故楠比呂志神戸大学准教授は生殖細胞の凍結保存を含め動物繁殖学の手法を駆使して希少野生動物の人工繁殖に挑戦した。同時に故佐藤哲也園長(神戸動物王国・那須動物王国)とともに希少動物人工繁殖研究会(現・野生動物保全繁殖研究会)を組織し、園館のスタッフと協働する、保全繁殖の潮流を創り出した。
彼らの衣鉢を継いだ楠田哲士岐阜大学准教授は繁殖生理状態を非侵襲的に把握することで、飼育下繁殖の成功率向上に貢献している。故人となられたお二人の先駆者の努力は今結実しつつある。
牧場実習で学ぶ!動物との向き合う経験

牧場実習では保定や削蹄などの管理実務を大家畜で学ぶ。この経験が動物園で大動物と向き合ったとき少しは生きるかもしれない。
糞尿の臭いを敬遠して大動物に直接触れる貴重なチャンスを逃すのはもったいないことだ。夏休みを民間の牧場の住み込みや動物園での実習に費やす熱心な学生もいる。農用家畜あるいは動物園動物、いずれにせよ、自ら進んで飼育現場に入ることで得られる実践経験は個人の貴重な財産となる。
おわりに「未来の飼育員へ」
十八歳人口が減り続けている昨今、受験生確保に苦慮する大学は多い。近年、岐阜大学では応用動物科学コースの教員が中心となって動物園生物学研究センターを立ち上げ、動物園学の教育研究に本腰を入れた。ユニークなこの取り組みは大学の個性化につながると大学本部からの期待も高いのではないか。
岐阜大学での先進事例に学ぶところはあると思うが、大学が抱えている事情はそれぞれ異なる。宮崎大学畜産分野の場合、地元の畜産界からの期待に誠実に応えつつ、動物園人の後進育成を密やかにしぶとく続けていくことが最適解となろう。
「言うはやすし、行うはかたし」の難題ではあるのだが・・・。
少数でかまわない。腕のいい飼育員が私の第二の母校から登場することを願っている。
寄稿者profile
略歴
1974年 京都大学農学部農学科卒業。京都大学大学院農学研究科修士課程・博士課程を経て、財・環境科学総合研究所と財・自然農法国際研究開発センター技術研究部で研究員として勤務。1997年9月に宮崎大学農学部家畜生産学講座に講師として着任。助(准)教授そして教授を務め、2016年3月に定年退職。動物栄養学、飼料学、動物環境管理学、比較生理生態学、実践動物園学などの講義を担当した。
現在、九州医療科学大学非常勤講師と宮崎大学フロンティア科学総合研究センタープロジェクト研究員を務めている。

著書
冬眠する哺乳類(川道武男,近藤宣昭,森田哲夫 編著)東京大学出版会、2000年
訳書
都市に侵入する獣たち (川道美枝子・細井栄嗣・正木美佳・森田哲夫 共訳)築地書館、2024年